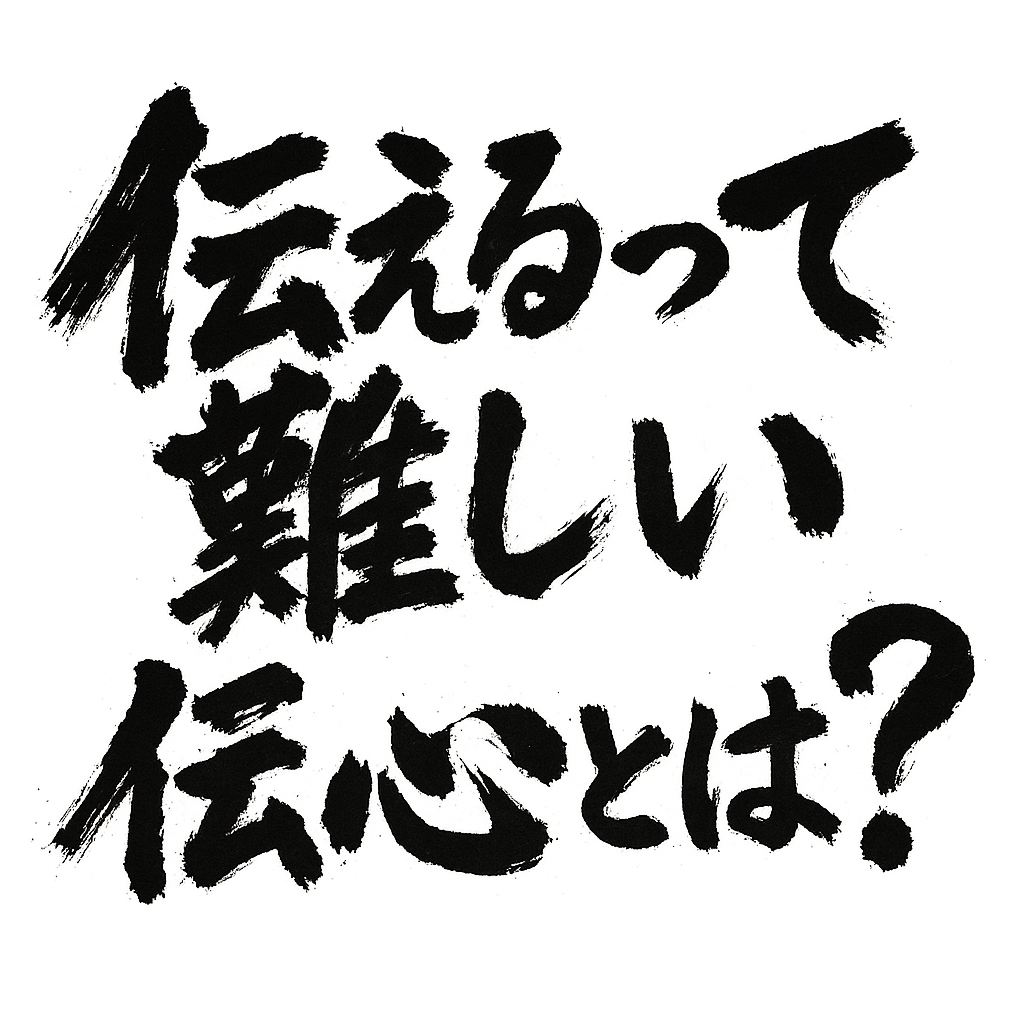【数字でハッキリ】農家の消費税、実は2割しか払ってない。でも5,000万超えたら地獄が待ってる話。
2025/04/06
知らなきゃ損する、消費税の仕組みと戦略
──売上3,000万から5,000万超の現実まで
ちょっとだけ、消費税の話を一緒に勉強してみませんか? 「うーん、税金の話は苦手だな」と思った方、ごめんなさい。けれど、これは農家として経営を発展させていく以上、いつか必ず向き合わなければならないテーマです。
できるだけやさしく、でもリアルに。そんな気持ちで書いています。
本題に入る前に、「そもそも消費税ってどういう仕組みなの?」という人のために、基本的なところを少しだけ説明しておきますね。
消費税は、商品やサービスを買うときに払っている税金のことです。スーパーで野菜を買えば8%、機械屋で部品を買えば10%。この消費税は、最終的には国に納められますが、実際に税務署にお金を納めるのは“商売している側”、つまり私たち生産者や販売者です。
たとえば白ねぎを1万円で出荷すると、消費税(軽減税率8%)は800円。これを買った卸売業者やスーパーは、私に1万800円を支払います。そして私は、この預かった800円を、後日まとめて国に納める義務がある、というのが大まかな流れです。
ただし、私たちが仕入れや経費として使った分にも消費税が含まれてますよね? たとえば資材を買って880円のうち80円が消費税だったら、その80円は「仕入れ時に払った消費税」として差し引いていい。
だから実際には、「もらった消費税」から「払った消費税」を引いて、その差額だけを納める。これが基本の仕組みです。
さらに細かく言うと、仕入れ時の消費税を正確に帳簿に残しておかないと、「差額を引いていい」とは認められません。そのため帳簿や証憑類の管理がとても大事になります。
その上で、「簡易課税制度」とか「本則課税」といった方式の選択があるわけです。
今日は、農家なら誰しも「うすうす気になってるけど、面倒で後回しにしがちな話」
そう、消費税について。
「消費税なんて、売上が増えたら税金で持っていかれるだけ」
「課税事業者になったら地獄」
そんなふうに思ってる人、多いと思う。
でもね、これ、正しくもあり、間違いでもある。
実は売上5,000万円までなら「簡易課税制度」っていうありがたい制度が使えて、消費税の8割は払わなくて済むんだよね。
でも、売上が5,000万超えた瞬間、この特典は消えます。
そのあとに待ってるのは…本当の地獄。
今日はそのリアルな話を、売上3,000万円の農家さんを例に、できるだけわかりやすく伝えます。
簡易課税って、実はめちゃくちゃお得
農家の場合、売上が1,000万円を超えると、2年後から課税事業者になります。これがいわゆる「消費税の壁」ですね。
そのときに選べるのが簡易課税制度。これは、帳簿をそこまで細かく付けなくても、ざっくりと納税額を計算できるというありがたい仕組み。
農業は、みなし仕入率が80%。
つまり、売上の80%は経費で消えたと見なして、残りの20%分に対してだけ消費税を払えばいいという話です。
たとえば、資材費や肥料、燃料代、機械修理代など、毎年それなりに出費してますよね。 それを「実際いくら使ったか」ではなく、「まあだいたい8割使ったでしょ」とみなしてくれるわけです。
経理が苦手な人でもこれなら安心。税理士にお願いするにもコストが抑えられるし、何より納税額が少なくて済む。
しかも、予測がしやすいのも利点です。毎年の納税額がある程度読めるというのは、資金繰り計画を立てるうえで大きなメリット。
簡単で、負担が軽くて、現場の感覚にも合ってる。
正直、使えるうちは使ったほうがいいです。
【具体例】売上3,000万円の場合
たとえば、ある農家さんの年間売上が3,000万円だとしましょう。これは中規模の農家さんなら現実的な数字です。
青果物なので、消費税は軽減税率8%。
取引先から預かる消費税は、3,000万円 × 8% = 240万円。
ここで簡易課税を選んでいると、その240万円のうち20%だけ納税すればOKになります。
つまり、240万円 × 20% = 48万円。
預かった240万円のうち、48万円だけ納税。残り192万円は経営資金として自由に使えます。
これを売上で割ると、実質の消費税負担は売上の約1.6%。
一見「消費税8%ってキツいな…」と思いがちだけど、実態としてはその5分の1しか払っていないのが現実なんです。
しかもこの金額なら、経費や機械更新が重ならない年はキャッシュフロー的にも回しやすい。
農業経営の中では資金が詰まりやすい時期が何度もあるけど、簡易課税の納税負担ならまだ調整が効く。
だからこそ、簡易課税は農家にとって非常にありがたい制度なんです。
でも、売上5,000万円超えたら終わり。
「簡易課税、なんて素晴らしいんだ」と思ったあなた。
ちょっと待って。現実はそんなに甘くない。
この制度、ずっと使えるわけじゃありません。
前々年の課税売上高が5,000万円を超えたら、簡易課税は使えません。
つまり、売上が伸びて5,000万円を超えたら、その2年後から自動的に本則課税に切り替わります。
本則課税になるとどうなるか?
実際に支払った経費の証明が必要。帳簿の記帳も一気に複雑に。
「みなし」で済んでいた時代が終わり、「実績」で証明しなきゃいけなくなる。
しかも、設備投資が少ない年だったり、経費の消費税が少なければ、控除額が減って納税額が跳ね上がる。
たとえば、売上5,500万円、経費の支出がやや抑えられていた年。
納税額が200万円以上になることは普通にあります。
これ、簡易課税だった頃の4倍以上。
「えっ、こんなに払うの…?」って本気でゾッとする金額です。
売上が増えた分の喜びなんて一瞬。
気づいたら「売上の成長より納税額の成長のほうが速い」という現実が待ってます。
しかもこれ、毎年やってきますからね。
「消費税は預かり金だから問題ない」は幻想
「消費税はお客さんから預かったお金でしょ?払えばいいだけじゃない?」
たしかに理屈ではそうです。
でも、現場の農家にとっては、その“預かり金”が実際には手元の運転資金に溶けていくのがリアルなんです。
たとえば、こんなことありませんか?
-
ハウスの屋根が破れた。急いで修理、30万。
-
思わぬ病害虫被害で、農薬や対応資材に追加出費。
-
肥料代が年々高騰し、思ったより出費がかさんだ。
こんな日々の「想定外」が重なっていくと、いつの間にか「預かったはずの消費税」は通帳から消えている。
納税時期に「あれ?思ったより口座残ってない…」って青くなった経験、私もあります。
だからこそ、私は消費税を“払わないといけない経費”として把握しています。
これだけで、年度末の安心感が全然違う。
また、事前に資金繰り表を作って、1年のどこでお金が足りなくなりそうかも確認しています。消費税の納税タイミングと被る時期に他の大きな出費が重なると、ほんとに危ない。
まとめ:消費税は「ちゃんと備える人」だけが乗り越えられる
-
売上3,000万円 → 簡易課税で納税48万円(実質1.6%)
-
売上5,000万円超 → 簡易課税NG。納税額は一気に200万円超えもあり得る
消費税は、「仕組みを知って、対策している人」にとっては怖くない。
でも、知らなかった・準備してなかったというだけで、資金繰りが一気に詰まるほどの破壊力を持ってます。
私のように独立して少しずつ規模を広げてきた農家こそ、今のうちから備えるべき。
「売上を伸ばしたい」なら、同時に「税金にどう対応するか」もセットで考えるべきなんです。
たとえば、売上4,800万円で止めておくという判断も、実は立派な戦略です。中途半端に5,100万円まで増やしてしまうと、簡易課税が使えなくなって損することもある。
「知らなかった」で済まされない世界だからこそ、農家も自ら学び、判断する力を磨いていく必要があります。消費税は単なる“事務”や“税金”の問題ではなく、経営に直結する重要なテーマです。制度を知り、自分の経営に落とし込む力こそが、これからの時代を生き抜く農家に求められる「経営者としての知性」なのだと思います。
今後も、こうした消費税に対して持っている私の疑問や実務の中で感じる違和感、さらには制度の変化への対応などについて、農家の目線で発信していきたいと考えています。
ちなみに、一度課税事業者になったとしても、状況によっては再び免税事業者に戻れる場合があります。たとえば、基準期間(2年前)の売上が1,000万円以下であれば、原則としてその2年後には再び免税事業者の扱いに戻れます。
ただし、自分からインボイス登録をしている場合には、免税事業者の条件を満たしても形式上は引き続き課税事業者のままとなります。こうした仕組みもまた、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。複雑で見落とされがちなテーマだからこそ、丁寧に学び合える場をつくっていければと思います。