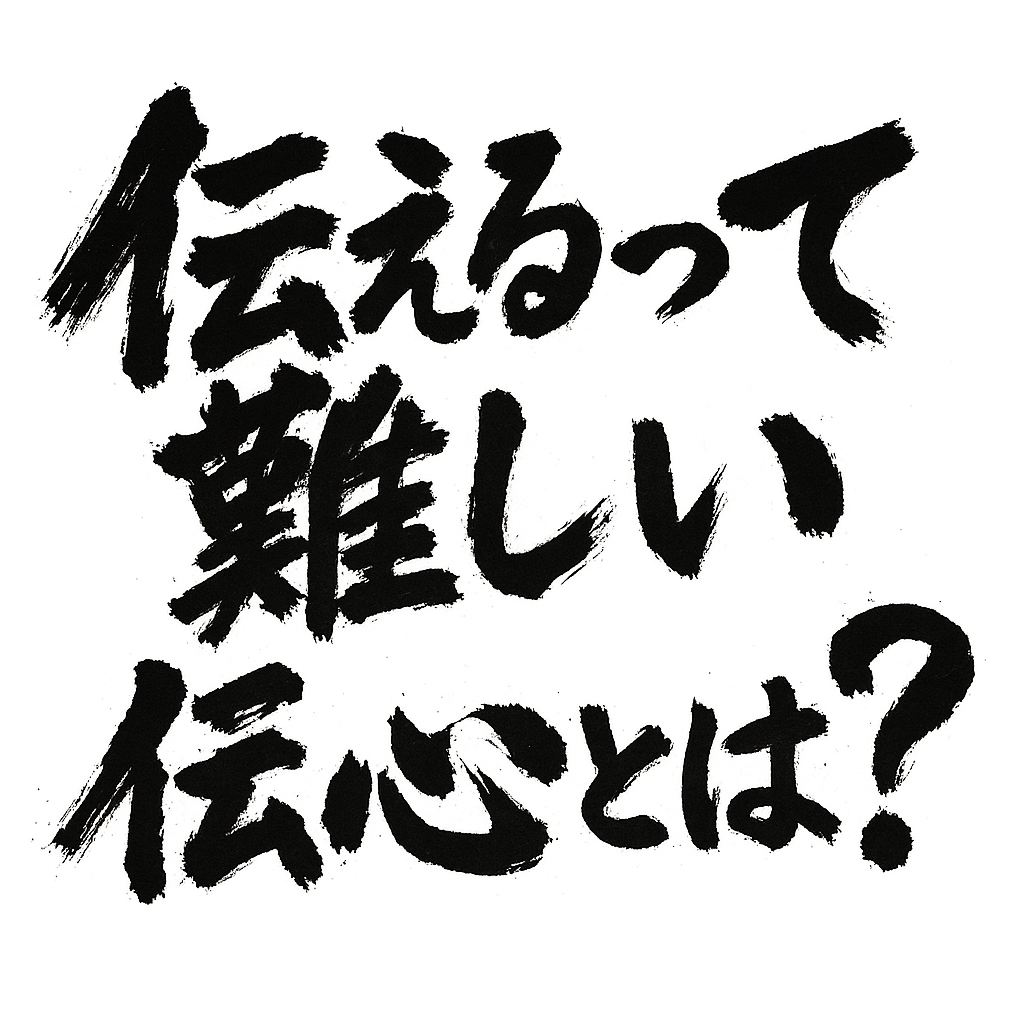ファーマーズマーケットとプロ農家の矜持
2025/04/08
「再生産価格で売れない場所に、私たちの野菜は出さない」
出さないと決めた理由
私はこれまで一度も、地元のファーマーズマーケットに出荷したことがない。
別に出せなかったわけじゃない。出そうと思えばいつでも出せる。でも出さないと決めている。それは、「安く売るために野菜を作っているわけじゃない」からだ。
ファーマーズマーケットには、当然、地元の農家さんたちがたくさん出している。正直、凄く質の良い野菜ばかりだが、その価値に見合った価格設定がされていないと感じる、出荷基準があるわけでもないから、形も大きさもまちまち、パッと見たら「家庭菜園の延長」みたいな品物もある。
私が問題だと感じるのは、価格だ。
スーパーの市況より2〜3割安いなんて当たり前、中には「どう考えても原価割れしているだろ」という価格で売っている人もいる。たしかに、消費者目線では「安くて新鮮で地元産」という魅力がある。でもそれは、本当に消費者の為なのだろうか?
年金があるから赤字でもいい。生活の足しになればいい。そんな感覚で売られる野菜が、地域の価格の基準になってしまうのは、あまりにもおかしい。
私たちのように農業一本で食べている人間は、そんな値段で野菜を売っていたら潰れてしまう。人を雇って、資材を買って、土作りをして、収穫して、皮をむいて結束して、袋詰めして、そのうえで「再生産」できる価格でなければ、野菜作りなんて続けられるわけがない。
さらに言えば、価格を下げてしまうことで、自分たちの労働や経験、積み重ねてきた技術の価値までもが安く見られてしまう。それが積もり積もって、「農業は安くて当たり前」「野菜はタダ同然で売られるもの」と思われる風潮に繋がる。
だから、後藤農園は出さない。 いや、出すべきではないと思っている。
兼業農家と価格崩壊の構造
ファーマーズマーケットで安売りしているのは、たいていが兼業農家か高齢の年金農家だ。もちろん、そういう人たちが農業をやるなとは言わない。むしろ、地域の農地を守るという意味ではありがたい存在でもある。
ただし、そこには“構造的な歪み”がある。収入のメインが別にある、あるいは年金をベースに生活が成り立っている人たちは、赤字を気にせずに農産物を出荷できる。その結果、無意識のうちに「価格破壊」が起こってしまう。
「売り先があるから作ってみよう」「余ったから持っていこう」というスタンスで野菜が市場に並ぶと、どうしても価格の整合性が崩れてしまう。特に、赤字でも年金で暮らせる人たちが市場に大量に野菜を出すと、それが「地域の相場」になってしまう。
本業の農家がそれに巻き込まれてしまったら、もうやっていけない。農業だけで生活している農家が、その価格帯に付き合わされたら、それはもう「自殺行為」に等しい。
市場原理が働かない場所で農産物が動くというのは、農業そのものの健全性を脅かす行為だと私は思っている。生活の手段として農業を選び、人生を賭けて畑に立っている人たちが、余暇の延長として野菜を作る人たちと同じ舞台で戦わされるのは、不条理でしかない。
そういう矛盾が、今の直売所やファーマーズマーケットの至るところに潜んでいる。そして、それに声を上げる人は少ない。
農業は“ついで”ではできない
農業というのは、決して片手間でできるものではない。天候に振り回され、土と対話しながら、作物の機嫌をうかがい、収穫に至るまでに膨大な労力と時間とコストがかかる。
虫の動き、土壌の水分、朝露の湿り具合──そういった日々の細やかな観察が品質に繋がる。農業には“感覚”と“論理”の両方が求められる。
それでもなお、まともに生活を成り立たせるためには、収穫した作物を適正な価格で販売できなければ意味がない。
「とりあえず作って売ってみよう」「安くても売れれば嬉しい」 そんな感覚で農業が行われると、結局、本気で農業を仕事として選んだ人たちが損をする。
趣味としての農業と、職業としての農業。その線引きが曖昧なままでは、日本の農業の未来は守れない。
本気でやる人がバカを見る。そんな業界に誰が飛び込もうと思うだろうか? 農業が“未来ある仕事”であるためには、やる側の覚悟と、買う側の理解の両方が必要だ。
“再生産価格”の意味を考える
私がここで何度も言っている「再生産価格」とは、簡単に言えば「次の作付けができる価格」だ。資材費、燃料費、労働力、機械の維持費など、すべてを含めて、次の年もまた同じ品質の作物を育てるために必要な最低限の価格のことだ。
それに加え、機械の更新や施設の補修、研修費用や人材育成といった“未来への投資”も、本来は再生産価格の中に組み込まれるべきだと私は思っている。
これを割り込んだ価格で売ってしまえば、翌年以降の農業が立ち行かなくなる。まさに“自分の首を絞める”ようなことになる。
ファーマーズマーケットで売られている価格の多くは、この再生産価格を明らかに下回っている。だから私はそこには出さない。
これは戦略ではなく、矜持の問題だ。
私たちはただ野菜を売っているのではない。農業の価値と未来を売っている。その自覚を持って価格をつけなければ、本当の意味で「農業を続ける」ことはできない。
誰もが“安さ”だけで野菜を選ぶようになったら、やがてそのツケは消費者自身に返ってくる。安いけれど栄養価の低い野菜。安いけれど誰も作らなくなった土地。そうなってからでは、もう遅い。
選ばれる農業になるために
後藤農園では、市況をある程度意識した価格設定をして、信頼できる取引先と契約して出荷している。再生産価格をきちんと理解し、それを受け入れてくれる相手としか取引はしない。買い叩かれるような取引は一切しないし、自分たちの手間と技術を正当に評価してくれる関係でなければ、長くは続かないと考えている。
その理由はシンプルだ。私たちは、目の前の売上ではなく、5年後、10年後も農業を続けられるかどうかを常に見据えている。価格の裏には、手間があり、汗があり、時には失敗から学んだ知恵がある。そうした“見えない価値”まできちんと理解してくれる取引先としか、本当の意味で信頼関係は築けない。
私たちは単に「作って売る」ことを目的にしていない。自分たちが育てた作物が、どのような場所で、どんなふうに並び、どんな人の手に渡るのか。そのプロセスまで含めて「農業」だと考えている。食卓に並ぶまでの流れに責任を持ちたいし、自分たちの名前がついた野菜がどう扱われるのかも重要だと思っている。
短期的な売上や回転率よりも、長期的な信頼関係と持続可能な農業を重視している。1年2年ではなく、10年、20年続けていける相手とつながっていくことが、私たちの理想だ。そのためには、一時的な価格競争ではなく、お互いの考え方や理念を共有できる関係性が重要だ。その関係性があるからこそ、時には値段以上の価値を生み出すこともできる。
「どこに売るか」ではなく、「どういう関係で売るか」。それが今の農業には求められていると感じる。売値が高いか安いかだけではなく、その背景にある“理解と敬意”があるかどうかで、こちらの覚悟も変わってくる。たとえ同じ価格で買ってくれるとしても、「なぜその価格なのか」をきちんと説明し、理解しようとしてくれる人と取引したい。
そして、私たちの野菜を必要としてくれる人に、必要な形で届ける努力を惜しまない。そのために、ホームページやSNSを活用して、農園の想いや姿勢を日々発信している。農業という仕事の背景にある現実や苦労を伝えることも、信頼を築くための大事な一歩だと思っている。
ファーマーズマーケットに出荷しないというのは、「売り先を選ぶ戦略」ではなく、「価値を守るための哲学」だ。安さで評価されるのではなく、考え方や品質、取り組みの姿勢で選ばれる農業を目指している。その農業が“選ばれる存在”であるために、日々の姿勢や積み重ねが大事なのだ。
価格で勝負しない。 信頼で勝負する。 誠意と継続で勝負する。 覚悟と発信で勝負する。
それが私たちが目指している農業の形だ。
農業一本で生きられなければ、日本は終わる
「農業一本では生活できない」、「親がやっていたから仕方なくやっている」そんな職業を、若者が選ぶわけがない。断言できる。夢も未来も感じられない職業を、自ら進んで選ぶ人はいない。
「農業だけじゃ食えない」という言葉が常識になった瞬間、日本は自らの未来を閉ざすことになる。それは農村の問題ではなく、国全体の“食”の持続可能性が崩れていくサインだ。
土を耕し、作物を育て、それを食卓に届ける。そのすべてに真剣に向き合い、暮らしを成り立たせる職業としての農業が、きちんと尊重されなければならない。そこには天候への対応力、技術、経営判断、販路の開拓といったあらゆる力が求められる。農業は単なる作業ではなく、“総合職”なのだ。
趣味で野菜を作る人を否定はしない。むしろ、自分たちの暮らしを自らの手で支えようとする精神には尊敬すら覚える。ただ、それが本業の農家の生活を脅かす存在になっている現実を、私たちは直視する必要がある。
地域で一所懸命に作られた野菜が、価格競争に巻き込まれて価値を失っていく。その背景には、「副業でも農業はできる」という誤った認識と、「安いものを買いたい」という消費側の意識がある。こんな物価高の時代なので理解はできるが。
若者が夢を持って飛び込める農業を取り戻すには、「ちゃんと暮らしていける」ことが最低条件だ。しかもその「暮らし」とは、ただ生きていくための最低限ではなく、自分の仕事に誇りを持ち、人生を投じるに足るだけの安心感と希望が伴う暮らしでなければならない。
「食べていける」ということは、単に生計が成り立つだけじゃない。家族を作り、養い、従業員に賃金を払い、未来のために投資ができること。自信と誇りを持って続けられるということだ。
それができない国は、やがて食を自給できなくなる。気がつけば農村は空洞化し、農業インフラは崩れ、食料のほとんどを海外に依存するようになる。そしてそれは、外部要因に弱い国になるということだ。
最後には、命の根幹すら外注しなければならなくなる。食卓に何を並べるかさえ、自分たちで選べなくなる。私はそんな生活はまっぴらゴメンだしそんな未来を、私は子どもたちに渡したくない。
それが、日本の終わりではなくて、何だというのだろう。
だから私は、プロの農家として、誇りを持って農業を続ける。
“安さ”ではなく“価値”で選ばれる野菜を育て、 “再生産”できる価格で販売し、 “暮らし”が成り立つ農業を守っていく。そして魅力ある農業を次の世代に渡したい。
本気でそう思っている。
プロ農家としての私の思いを書き綴ることが、未来の農業を守る手助けになると信じている。